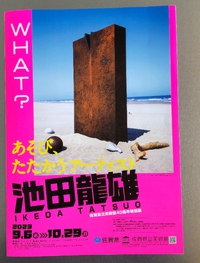2010年01月09日
伊万里焼の名称が消えていく
ご存知のように、肥前地区(佐賀長崎県)で焼かれた磁器が、伊万里の港から積み出されたことから伊万里焼と呼ばれるようになりました。
有田が日本磁器発祥の地なら、伊万里は日本磁器発祥の名称といっていいと思います。
近年肥前地区の焼き物は伊万里焼・有田焼・波佐見焼きなど各地名で呼ばれるようになっています。
ただ、中身はというとほとんど変わりません。
磁器の原料、釉薬、焼成方法は各窯元で多少の差があるだけで基本的には同じです。
歴史的に見ても商品に違いがないことからも、伊万里焼○○産とした方がもっとも分かりやすいと私は思っています。
お客様にとってもすっきりとして分かりやすいでしょう。
私が展示会で伊万里焼として販売していると、伊万里焼と有田焼はどう違うのですかとよく聞かれます。
そのたびに、同じだということをいつも説明しなければなりません。
しかし、地名で呼ばれるようになっている以上、それを受け止めながらやっていかなければと思っていました。
それなのに先日、東京の百貨店で目にしたのは、伊万里の窯元で焼いている焼き物が、ある商品は有田焼、ある商品は肥前鍋島焼と表示されていて伊万里焼の名称はどこにもありませんでした。
鍋島を使うなら伊万里焼鍋島調とするのがもっとも分かりやすいと思います。
どうしたのでしょうか?
話はちょっと変わりますが、コーヒーの「モカ」を多くの方がご存知だと思います。
この「モカ」という名称はアラビアで生産されたコーヒー豆がモカという港から積み出されたことから、「モカコーヒー」と呼ばれるようになったといわれています。
現在モカコーヒーの産地はアラビア半島南西部にあるイエメン共和国の山岳地帯とアフリカ大陸北東部にあるエチオピアの高原高地のようです。
モカという港は現在はなくなっているにもかかわらず、コーヒーの代表的な名称として使われています。
このことが何を意味するのか、肥前地区に住む私達は考えなければならないと思います。
有田が日本磁器発祥の地なら、伊万里は日本磁器発祥の名称といっていいと思います。
近年肥前地区の焼き物は伊万里焼・有田焼・波佐見焼きなど各地名で呼ばれるようになっています。
ただ、中身はというとほとんど変わりません。
磁器の原料、釉薬、焼成方法は各窯元で多少の差があるだけで基本的には同じです。
歴史的に見ても商品に違いがないことからも、伊万里焼○○産とした方がもっとも分かりやすいと私は思っています。
お客様にとってもすっきりとして分かりやすいでしょう。
私が展示会で伊万里焼として販売していると、伊万里焼と有田焼はどう違うのですかとよく聞かれます。
そのたびに、同じだということをいつも説明しなければなりません。
しかし、地名で呼ばれるようになっている以上、それを受け止めながらやっていかなければと思っていました。
それなのに先日、東京の百貨店で目にしたのは、伊万里の窯元で焼いている焼き物が、ある商品は有田焼、ある商品は肥前鍋島焼と表示されていて伊万里焼の名称はどこにもありませんでした。
鍋島を使うなら伊万里焼鍋島調とするのがもっとも分かりやすいと思います。
どうしたのでしょうか?
話はちょっと変わりますが、コーヒーの「モカ」を多くの方がご存知だと思います。
この「モカ」という名称はアラビアで生産されたコーヒー豆がモカという港から積み出されたことから、「モカコーヒー」と呼ばれるようになったといわれています。
現在モカコーヒーの産地はアラビア半島南西部にあるイエメン共和国の山岳地帯とアフリカ大陸北東部にあるエチオピアの高原高地のようです。
モカという港は現在はなくなっているにもかかわらず、コーヒーの代表的な名称として使われています。
このことが何を意味するのか、肥前地区に住む私達は考えなければならないと思います。
Posted by 青風 at 23:06│Comments(3)
│○日記
この記事へのコメント
も少し詳しくすると、
伊万里地区はヘッドクォーターとかプロデューサーとか問屋とか
広い意味のマネージメント機能部門を擁する地区であり、
伊万里地区と各生産地域は一体でありました。
なお、唐津郷で生産された陶器も扱っていました。
単なる輸送拠点ではなかったのです。
だから「いまり」と言われたのです。
ついでに、赤絵技法を柿家へ伝えたのは
伊万里地区の陶器商でした。
また、陶器商の中心街は河畔附近ではなく、
内陸部にあったことは、マメ知識。
伊万里地区はヘッドクォーターとかプロデューサーとか問屋とか
広い意味のマネージメント機能部門を擁する地区であり、
伊万里地区と各生産地域は一体でありました。
なお、唐津郷で生産された陶器も扱っていました。
単なる輸送拠点ではなかったのです。
だから「いまり」と言われたのです。
ついでに、赤絵技法を柿家へ伝えたのは
伊万里地区の陶器商でした。
また、陶器商の中心街は河畔附近ではなく、
内陸部にあったことは、マメ知識。
Posted by k at 2010年01月10日 02:39
しつこくすいません。
2.今の有田地区が形成される前、
たくさんのピンきりの窯元が藩内陸側に松浦地区に乱立し
統制が取れなくなったので、大半を廃業させ
残りを有田の谷に集積させただけなのです。
2.今の有田地区が形成される前、
たくさんのピンきりの窯元が藩内陸側に松浦地区に乱立し
統制が取れなくなったので、大半を廃業させ
残りを有田の谷に集積させただけなのです。
Posted by k2 at 2010年01月10日 02:53
Kさん
コメントありがとうございます。
先人達が苦労に苦労して伊万里焼を世界へ日本国中へ広めていったのですから、感謝をしながら、進取の気性を忘れずに突き進むしかないですね。
私は伊万里焼を自信を持って広めていきます。
コメントありがとうございます。
先人達が苦労に苦労して伊万里焼を世界へ日本国中へ広めていったのですから、感謝をしながら、進取の気性を忘れずに突き進むしかないですね。
私は伊万里焼を自信を持って広めていきます。
Posted by 青風 at 2010年01月11日 20:48